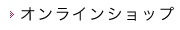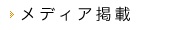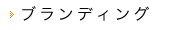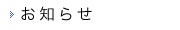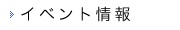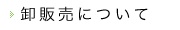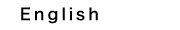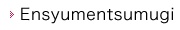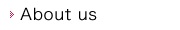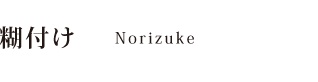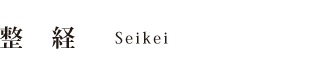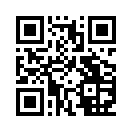2013年07月08日
遠州綿紬ができるまで

綿軸の原料となる綿の糸を、一定の長さの糸を巻いて束ねた「かせ」と呼ばれる状態に巻き取ります。きれいに巻けるように手作業で配慮をしながら、たくさんの糸を一気に巻き上げていきます。

糸を漂白(精錬)し、そのあとに指定の色を染色しす。糸を熱湯で洗う事で、植脂分やアクを落とし、糸に色が入りやすくなります。釜の中で、染料を溶かした熱湯をかけ、染めていきます。

糸の毛羽立ちを抑え、布を織りやすくするために、糊(のり)を糸に染み込ませます。織りの摩擦で糸が切れないようにする工程です。糊が温かいうちに糸量の割合を見てそれぞれつけ込み、均一に糊をよく馴染ませたあと、バタバタと少し仰ぎ整えます。

糸の束を、再び糸巻きへと仕上げます。染め、糊付けが終わった「かせ糸」を巻き取り、「いもくだ」という状態にします。糸が絡まないよう、切れないように、目を光らせて糸を巻き取ります。

たて糸を並べて、縞の模様になるように整えます。本数や色合いなど縞柄にはいくつもの組み合わせがあり、配列の順序によって縞柄が決まります。

整えた縞柄が崩れないように1本1本並べた順に、「おさ」と呼ばれる櫛状の穴の中に糸を通していきます。「おさ通し」が終わると、一斉に糸を巻き上げます。

たて糸を「機(はた)」にのせ、織り上げていきます。よこ糸に何色を使うかによって、仕上がりの色合いが変わってきます。1つの織機で、1日に約3~5 反、ゆっくりと織り上げていきます。

さまざまな工程を経て、遠州綿紬(えんしゅうめんつむぎ)として織り上がります。江戸時代から現代まで、数千種類以上の縞柄が生まれ、着物から雑貨まで広く愛されています。

Posted by 遠州綿紬のぬくもり工房 at 19:45